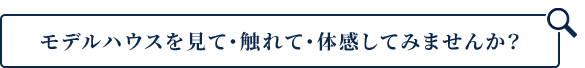2025.03.25
「建ぺい率・容積率・斜線制限・用途地域」って?土地探しするなら知っておきたい基礎知識
お家づくりを考え始めたばかりの方にとって、土地に関するルールや制限は少し難しく感じるかもしれません。
ただ、何も知らずに土地を選んでしまうと、「思っていたより建物が狭くなった」「せっかく考え抜いた希望の間取りが入らない…」なんてことになりかねません。
今回は、そんなちょっぴりハードルの高い土地の基礎知識、特に「建ぺい率」や「容積率」、「用途地域」などについて、なるべくわかりやすくお話ししていきます!
目次
「土地の広さ」の制限…「建ぺい率・容積率・最低敷地面積」
まずは、土地の”広さ”について考えていきましょう。
建てたいお家が本当に建築できるかどうかは、単に土地の面積だけではなく、法律で決められた「建ぺい率」や「容積率」も関係してきます。
建ぺい率
建ぺい率とは、「土地の広さに対して、どれくらいの面積の建物を建ててもいいか」を決めるルールです。
求め方は下の画像①の通りで、例えば、100㎡の土地に建ぺい率50%の制限がかかっている場合、最大で建築面積(建物を真上から見た時の面積で、通常は1階部分の床面積を指す)50㎡の建物を建てることができます。この建ぺい率の数値が低ければ低いほど、建物の面積も小さくなります。
ここで重要なのは、もし広い土地があっても、建ぺい率が低ければ十分な広さのお家を建てられない可能性があるということです。特に「平屋を建てたい!」という方は要注意。通常2階に設置されがちな子供部屋や主寝室をワンフロアでおさめなければならない平屋は、一般的に二階建てより1階の床面積が大きくなるので、建ぺい率の制限によっては思うような間取りがつくれないこともあります。
だからといって、わざわざ高い建ぺい率の土地を探すのは現実的ではありません。
敷地に対してめいいっぱい建物を建てると、隣家との距離が近くなり、火災が起こった時にすぐ延焼してしまう危険があります。また、風通しや景観の観点からもあまり望ましくないとされています。
そのような事情があるからこそ、前以って建ぺい率が定められているのです。
容積率
容積率とは、「土地の広さに対して、建物の延床面積(各階の合計面積)の上限はどれくらいか」を決めるルールです。
画像②の例では、100㎡の土地と、延床面積が75㎡(50㎡+25㎡)の建物があります。このパターンにおける容積率を計算すると、75%という数字が出てきます。もしも画像②の土地の容積率が75%以上に指定されていれば問題なし、それ以下であればこの建物は既存不適格建築物または違法建築物ということになってしまいます。
ちなみに、容積率はそれぞれの地域の都市計画によって定められていますが、前面道路の広さとも関係しています。また、様々な緩和条件も存在しているため、正しい住宅知識のある人に相談してみるのが良いでしょう。
容積率を設定する目的の一つは、地域の環境維持のためです。人口集中を抑制したり、高層建築物の乱立を防いで日当たりを適切に確保したり、地域に暮らす一人ひとりが快適な生活を送るために設けられています。
最低敷地面積
最低敷地面積とは、「この地域では、最低でも○○㎡以上の広さがある土地でなければ、その上に建物を建築してはならない」というルールです。
例えば、ある地域で最低敷地面積が150㎡と決められているのなら、100㎡の土地を買ってもお家は建てられません。
これは、ミニ開発などを制限するためにあります。ミニ開発とは「1,000㎡未満の土地を細分化し、敷地面積が100㎡未満など、小規模な宅地の分譲や建売住宅を開発すること」を言います(出典:SUUMO住宅用語大辞典より)
ミニ開発によって生み出されたものは低所得者層でも購入しやすいというメリットがある一方で、住環境や防災面で将来的なリスクを生むというデメリットも持っています。
土地を買って建物を建てたり、そのために土地の分筆を行いたい方は、この最低敷地面積も忘れずに確認しておきましょう。確認方法としては、地域ごとの自治体ホームページに公開されています。分からない場合は、役所に電話もしくは訪問すれば教えてくれるかと思います。
「建物の高さ」の制限…「斜線制限・絶対高さ制限」
次は、建物の”高さ”についてです。
地域によっては、建物の高さに制限がかかる場合もあります。
斜線制限
代表的なものとして、以下の3つがあります。
- 道路斜線制限:道路に面する建物の高さを制限するルール
- 隣地斜線制限:隣地との良好な環境を保つために建物の高さを制限するルール
- 北側斜線制限:北側の住宅の日当たりを守るために建物の高さを制限するルール(主に住宅地で適用)
こちらは、後述する「用途地域」によって制限の程度が変わってきます。
例えば「○○エリアで二階建てを建てたい!」と希望していても、北側斜線制限が厳しい地域では、2階部分が斜めにカットされるような設計になってしまうことも。とはいえ、斜線制限にも多くの緩和条件が設けられています。
この辺りは複雑ですので、「こういうものがあるんだな」程度の認識で全く問題ありません。ただ、実際に住宅会社と契約を結び、設計士からちゃんとした図面が上がってきたタイミングで、斜線制限というワードが出てくることがあるかもしれません。その時は「ああ、そういえば斜線制限っていう守らないといけない法的なルールがあったなぁ」などと思い出していただけると嬉しいです。もちろん設計士も、お客様側が斜線制限を完璧に理解している前提で話したりはしないと思うので、安心してくださいね。
絶対高さ制限
建築基準法には「絶対高さ制限」という、第一種低層住居専用地域などの特定の地域において、建築物の高さを一定以下に抑えるルールも存在します。
具体的には、10mか12mで設定されていますが、二階建て以下であれば基本的にその高さを上回ることはないので、あまり気にしなくて大丈夫です。ただし、三階建てをご希望の方はご注意ください。
なお、絶対高さ制限は容積率より優先度が高いため、仮に容積率の範囲内でも絶対高さ制限を超える建物は建てられません。
また、マンションやビルが多いエリアでは、「日影規制」というルールがあり、冬至の日を基準として、一定以上の日陰をつくらないような設計が求められることもあります。
「用途地域」
最後に、「用途地域」について説明します。これは、「このエリアにはどのような建物を建てていいのか」を決めるルールです。
自分が住んでいる住宅街に、突然大きな工場が建ってしまったら、正直困りますよね? そのようなことが起きないようにするのが、用途地域の役割なのです。
用途地域は全部で13種類あり、住居系が8種類、商業系が2種類、工業系が3種類という風に分けられます。
下記にそのうちの5種類をピックアップさせていただきます。
- 第一種低層住居専用地域:静かな住宅街。高さ制限が厳しく、三階建てが難しいことも。
- 第一種住居地域:住宅中心だが、小さな店舗や事務所も建築可。
- 近隣商業地域:住宅のほか、スーパーや飲食店もOKなエリア。
- 商業地域:ビルやマンションが多いエリア。住むこともできるが、騒音や交通量が多め。
- 工業地域:工場が中心で、住宅は基本的に建てられない。
このように、建てられるお家の広さや高さ、周辺環境は用途地域によって異なります。
その土地がどんな用途地域に指定されているかどうかは、各市町村の都市計画で公表されています。スマホやPCで比較的簡単に調べられるので、気軽に検索してみてくださいね。
まとめ
ここまで、このコラムを読んでいただきありがとうございました。
大切なお家づくりを成功させるためには、土地のルールを理解しておくことが必要です。
①土地の広さの制限(建ぺい率・容積率・最低敷地面積)
②建物の高さの制限(斜線制限・絶対高さ制限)
③用途地域(どんな建物がどこに建てられるか)
3つのポイントをしっかり抑えて、今後のお家づくりに役立てていただけると幸いです。
もし土地探しやプラン作成で不安がある方は、ぜひ住宅メーカーのスタッフに相談してみてください。プロとして、より詳しく丁寧にお答えさせていただきます!
WRITER

北川 智彬
営業
毎日が勉強の日々です。一生懸命頑張ります!
カテゴリで絞り込む
ARCHIVE
過去の記事
閉じる