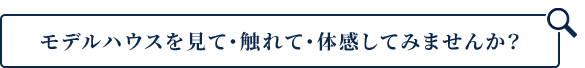2022.05.24
贈与にかかる税金はいくらから?住宅資金の贈与について
お家を建てる際には、ご両親やご親族からの金銭的な援助を得られる場合もあるでしょう。
しかし、よく調べずに贈与を受けると、多額の贈与税を支払うことになるかもしれません。
今回は、せっかくの援助を無駄にしないために、贈与税の基礎知識や注意点を解説します。
なお、税務相談は税理士の独占業務(その資格を持つ人しかできない仕事)であるため、贈与税・相続税対策や具体的なアドバイスが必要な場合には税理士への相談が
必要です。
簡単なことであれば、地方税務署は無料で相談に乗ってくれるので、まずは税務署に相談するのもオススメですよ。

目次
-概要
-注意点
- その他の制度との併用は可能!
- まとめ
贈与税とは
そもそも贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。財産には現金以外にも様々なものが含まれますが、ここでは「お金」に焦点を絞ってお話したいと
思います。
贈与税は、毎年 1月1日~12月31日までの1年間に受け取った金額の合計から、基礎控除額(110万円)を差し引いた金額に課税されます。
つまり、110万円までの贈与は贈与税の対象にならないということですね。
(1年間にもらった財産 ― 基礎控除額)× 税率 = 贈与税

※一般贈与財産(特例贈与財産以外)と特例贈与財産(20歳以上の子や孫が直系尊属から受けた贈与)では税率が異なるため、注意が必要です。
住宅取得資金贈与の非課税枠について
一般的な贈与とは別に、お家を建てる際の贈与には大きな非課税枠が設けられています。
「住宅取得資金贈与」や「住宅資金控除」「住宅取得資金 非課税制度」など、様々な名前で呼ばれていますが、正確には「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
非課税」といいます。あまりにも長いので、ここでは単に「特例」と呼びます。
概要
令和4年1月1日~令和5年12月31日までの間に、直系尊属(両親、祖父母)から新築・リフォームなど住宅取得のための贈与を受けた場合に、
非課税限度額(省エネ等住宅:1000万円、それ以外の住宅:500万円)までの金額が、非課税になります。
「省エネ等住宅」と認められるには、
・断熱等性能等級4以上 または 一次エネルギー消費量等級4以上
・耐震等級2以上 または 免震構造
・高齢者配慮対策等級3以上
以上のいずれかに該当し、住宅性能証明書などで証明する必要があります。
必要な5つの条件
①取得する新築住宅の登記簿上の床面積が40㎡~240㎡であり、その半分以上が居住用であること
②受ける側の年齢が18歳以上であること
贈与を受ける日ではなく、受ける年の1月1日時点で18歳以上であることが条件となります。成人年齢の引き下げに合わせて2022年4月以降の贈与に適用されます。
それ以前の贈与は20歳以上が条件です。
③受ける側の所得が2000万円以下であること
贈与を受ける年の所得なので、もし前年の所得が2000万円を超えていても適用可能です。
④贈与を受けた年の翌年の3月15日までに入居すること
もし工事が終わらない場合でも、3月15日までに棟上げが終わっていれば、居住する意思があると認められるため大丈夫です。
申告の際にその旨を記載した約定書を添えて申告しましょう。そして、その年の12月31日までに入居をしている必要があります。
⑤贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までに申告すること
贈与を受けた年の翌年に忘れずに申告しましょう。もし何らかの事情で1日でも申告が遅れると、この特例を受けることができません。
注意点
・贈与を受けた全額を住宅取得に使わなければならない
この特例を使う場合は贈与を受けたお金を、家具の購入はもちろんですが、住宅ローンの返済にあてることはできません。住宅取得そのものに使う必要があります。
・非課税枠は贈与を受ける側が基準
仮に1000万円の非課税枠があるとしても、父親から1000万円、母親から1000万円それぞれ受けられるわけではありません。
受ける金額の合計が非課税枠に収まっていないと、贈与税がかかることになってしまいます。
・申告を忘れずに
条件でも書きましたが、この特例を使う場合は必ず申告が必要です。非課税枠に収まっているから申告しなくてよいというわけではありませんので、忘れず申告しましょう。
その他の制度との併用は可能!
贈与税の基本的な課税方法には「暦年課税の基礎控除」と「相続時精算課税」の2つがあります。先ほどの特例と、このいずれかとの併用は可能です。
それぞれの簡単な内容や例をご紹介します。
暦年課税の基礎控除
概要は先述しましたが、贈与税には1年間で110万円の基礎控除があります。この金額と先ほどの特例の非課税枠は併用することができます。
ですので、省エネ等住宅の場合は1000万円+110万円→1110万円まで、それ以外の住宅は500万円+110万円→610万円まで非課税ということになります。
また、この基礎控除部分については申告は必要ありません。
(例1)省エネ住宅を建てたAさんが、2021年の1月~12月の間に、父親Bから600万円、母親Cから600万円の贈与を受けた場合、90万円が課税対象となります。
600万円(Bから)+C:600万円(Cから)-110万円(基礎控除)-1000万円(特例)=90万円
※それぞれの人からの贈与に110万円までの基礎控除を受けられるわけではありません。
相続時精算課税
概要
「相続」と名前がついているので、相続税と関係があるのかな?と思った方もいると思いますが、その通りです!
簡単に言うと、通算で2500万円までの贈与税を相続が起きるまで後回し(相続税として扱う)にする制度です。
60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対して財産が贈与された場合に適用されるのが原則です。
特別控除額(2500万円)を超えない部分について、時期や回数を問わず、相続が起きたときに相続税のみが課税されます。
特別控除額(2500万円)を超える部分について、毎年1月1日~12月31日までの1年間で受け取った金額に一律20%の贈与税が課税されます。
また、相続時精算課税の対象者が複数人の場合は、それぞれの人からの贈与に2500万円までの特別控除額を受けられます。
注意点
この制度と先ほどの特例とを併用すると、最大で3500万円まで非課税となるので、とても魅力的に思えますが、この相続時精算課税制度には注意点があります。
一度相続時精算課税を選択すると、その後贈与者からの贈与はすべて相続時精算課税となります。
毎年の暦年課税の基礎控除枠(110万円)はなくなってしまうので、注意が必要です。そして、少額でも贈与を受ける度に、毎年申告が必要になります。
また、実際に相続が発生した場合には、贈与を受けていた分を財産として差し戻して計算することになるため、相続できる資産が少なくなるという可能性もあります。
それらのデメリットを理解した上で、利用するか検討していきましょう。
まとめ
今回は贈与税の基礎知識や注意点をご紹介しました。ここでは触れていない細かい条件や例外もあるので、ご不安な点がある方は、必ず税理士などへ相談を行ってください。また、建築や入居の時期は急な調整が利かないので、住宅メーカーとの信頼関係も大切になってきますね。タカノホームでは、建物だけでなく、資金計画や建築スケジュールもお客様一人ひとりに最適なご提案をさせていただきます。気になる方は是非お声がけください!
WRITER

近藤 智哉
営業
早くも入社10年目。趣味はカメラと車。 よりよいご提案ができるよう積極的に資格取得を目指しています!
カテゴリで絞り込む
ARCHIVE
過去の記事
閉じる