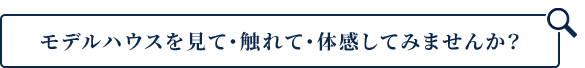2025.07.22
建てた後に後悔しない!ランニングコストを抑えるお家づくりのポイント4選
お家を建てることは、多くの人にとって人生最大の買い物です。土地費用、建物費用、諸費用など、初期費用(イニシャルコスト)だけでも非常に大きな費用がかかってきます。
しかし、住まいにかかる費用はこれだけではありません。忘れてはいけないのが、「ランニングコスト」です。建てた後、快適な暮らしを長期間維持するための費用がかかります。
たとえば「将来何が起こるか分からないし、なるべく費用を抑えたい」と、建築時のイニシャルコストを抑えてお家づくりを進めたとしても、住んだ後の光熱費や修繕費といったランニングコストが高ければ、結果的に割高な買い物になってしまうこともあります。
そこでこの記事では、「ランニングコストが抑えられる住まい」にするためにはどうすれば良いのか、一つずつ解説していきます。
目次
- ランニングコストとは?
- ランニングコストを抑える方法
-光熱費
-保険料
-固定資産税
-メンテナンス費用 - まとめ
ランニングコストとは?
住宅におけるランニングコストとは、住み続けるために必要となる継続的な費用のことです。具体的には以下のような支出が該当します。
- 電気、ガス、水道といった光熱費
- 火災保険、地震保険などの保険料
- 固定資産税
- 定期的なメンテナンス費用(屋根、外壁など)
これらは一度の支出ではなく、10年、20年、30年と住み続ける中で繰り返し発生するコストです。安価に建てられたお家でもランニングコストがかさめば、トータルの費用では高価なのに住み心地は全然良くないお家となってしまうことも少なくありません。
それでは、本題の「ランニングコストが抑えられる住まいをつくる方法」について早速見ていきましょう。
ランニングコストを抑える方法
ランニングコストを抑える上で、最も即効性があり、日常的に恩恵を感じられるのが光熱費の削減=冷暖房効率の良さです。
では、冷暖房効率が高いお家とはどのような特性を持っているのでしょうか。
Ⅰ 断熱性能×気密性
冷暖房効率に最も影響を与えるのが「断熱性能」と「気密性能」です。
断熱性が低いお家では、冬は暖めた空気が逃げ、夏は外の熱気が入り込みます。結果、エアコンの稼働時間が長くなり、電気代がかさんでしまいます。
一方、高断熱住宅は、一度冷やしたり暖めたりした空気が長く保たれます(これは魔法瓶のような構造をイメージすると分かりやすいですね)
さらに、気密性が高ければ隙間風による温度のロスを防ぎ、計画的な換気も可能になりますので、エアコンの電気代がお安く済みます。
断熱性能・気密性能の良し悪しを判断する基準としては、住宅性能表示制度などで確認できる「UA値(外皮平均熱貫流率)」、「C値(相当隙間面積)」が挙げられます。
UA値・C値ともに数値が低いほど優れており、これらは断熱材の貼り方や使用している素材によって変わってきます。
なお、この辺りの詳細は過去のコラムにて解説していますので、お時間のある方は下記の記事もぜひご確認ください。
お家の「気密性」は大丈夫?断熱と合わせて大切にしたい「気密」の話
Ⅱ 窓
窓から逃げる熱の量は、なんと住宅全体の約50%とも言われています。
せっかく高断熱仕様で建てたお家も、窓がただの単板ガラスでは断熱効果は半減!
代わりに「複層ガラス」や「トリプルガラスを採用した断熱サッシ」を使えば、単板ガラスよりも熱の出入りをしっかり抑えることができます。また、アルミサッシではなく「樹脂や木製のサッシ」を選ぶと、より断熱性が高まります。
初期費用は上がるかもしれませんが、冷暖房効率が大きく向上するため、長い目で見れば十分元が取れる投資です。
窓に関するお話についても、既に過去のコラムで紹介しています(涼しくて電気代も節約できるお家にしたいなら「窓」にこだわるべし!種類や選び方を解説)
Ⅲ 太陽光発電
太陽光発電は、自宅の屋根で電気を自家発電する仕組みです。発電した電気を自身の住まいに使用することで、電力会社から買う電力量を減らせるため、電気代=光熱費が大幅に削減できます。
もう少し具体的に言うと、太陽光パネルでつくった電気は、まず家庭内で優先的に電力消費されます。仮に、昼間に太陽光パネルで1kWh発電し、その1kWh分を家庭内で使えば、通常なら電力会社から買っていた約30~40円の電気代がまるごと不要になります。
さらに、日中使い切れずに余った電気は、電力会社に売ることができます。売電価格は年々下がってきてはいますが、それでも1kWhあたり10円以上(2025年時点)で売電できるケースが多く、お小遣い収入のような形で家計をサポートしてくれます。
近年、電気代は年々上昇傾向にあります。将来的にもこの傾向が続く可能性は高く、自家発電できる住まいはそれだけで強みになります。
とはいえ、太陽光発電にもデメリットはあります。詳しくはこちらのコラムで!(太陽光発電は導入すべき?メリットデメリットは?)
意外と見落としがちなのが、「火災保険」と「地震保険」。これらも定期的に更新が必要なランニングコストの一部になります。
実はこの保険料、お家の構造によって負担額が変わることをご存知でしょうか?保険料を少しでも抑えるためには、以下の2点がカギになります。
-
火災保険料を抑えるなら…「省令準耐火構造」を採用すること!
-
地震保険料を抑えるなら…「耐震等級3」を取得すること!
まず、省令準耐火構造とは、住宅金融支援機構が定める火に強い木造住宅のことです。
主な特徴は、隣家からの火が移りにくい外壁仕様、室内で火が広がりにくいファイヤーストップ構造、天井裏や壁内の配線まわりの耐火対策などです。
準耐火建築物まではいかなくても「一定の防火性能がある」と認定された構造のため、火災保険料は半額になります。
続いて耐震等級は、建物の地震に対する強さを示す指標です。等級は1~3まであり、数字が大きいほど耐震性能が高くなります。
耐震等級3を取得すると、地震保険料は半額です。理由としては、倒壊リスクが低く、保険会社にとっても保険金を支払う可能性が少ないため、優良物件と評価されるからです。
例として、一般的な木造住宅+耐震等級1の場合と、省令準耐火構造の木造住宅+耐震等級3の場合の保険料を比較してみます。
- 一般的な木造住宅+耐震等級1の場合…火災保険+地震保険で30万円(5年間)
- 省令準耐火構造の木造住宅+耐震等級3の場合…火災保険+地震保険で15万円(5年間)
このように、前者と後者では大きな差が出てきます。
ただ、保険関係は難しい部分もあるかと思いますので、こちらのコラムも一読いただけると嬉しいです(お家づくりにまつわる保険とは?後回しになりがちな「火災保険」や「地震保険」について解説)
固定資産税もお家を所有している限り、毎年発生する税金になります。
建物と土地それぞれに課税されますが、建物の評価額は構造、面積、材料の種類によって決定され、初年度の金額を基準に数年かけて減価していきます。
注意したいポイントとしては、税金が安い=おトクと単純に考えるのではなく、トータルコストとメンテナンス性を鑑みて判断することです。
たとえば、耐久性の高い建材を使用したお家は、評価が上がる反面、メンテナンス費用は少なくなるはずです。
反対に、小さなお家は固定資産税が安くなりますが、将来的な使い勝手とのバランスが重要になってきます。
ただ、長期優良住宅の認定を受けた住まいは、固定資産税の減税期間が一般住宅の場合3年間であることに対し、5年間に延長されるため、できれば長期優良住宅にすることをおすすめします(長期優良住宅とは?2022年10月の改正について解説!)
意外と大きな負担となるのが、外壁・屋根のメンテナンス費用です。
築10年~15年で再塗装や補修が必要になるお家もあり、これを怠ると雨漏りや断熱性の劣化に直結してきます。
しかし、高耐久の外壁材と屋根材を最初から選ぶことで、メンテナンスサイクルを延ばすこともできます。
外壁材の場合なら、サイディング(高耐候仕様)材を使用すると30年~40年持つものもあります。
屋根材の場合は、ガルバリウム鋼板を使用することで、軽量で耐久性が高く、錆にも強くなります。
もちろん、外壁と屋根は外観のデザイン性に大きく関わってくるパーツのため、一概に「サイディングとガルバリウムが絶対おすすめ!」とは言えません。ちょうどこの2つをテーマにしたコラムを過去に執筆しているので、以下の記事も参考にしていただき、自分たちの理想の住まいにとっての優先順位を考えた上でご検討ください。
まとめ
住宅は建ててからが本番です。初期費用を浮かせるために安く建てたお家が、10年、20年…と暮らす内に光熱費、保険料、修繕費といったランニングコストで家計を圧迫してしまう例は少なくありません。
一方で、冷暖房効率の良い高断熱高気密住宅は、光熱費を抑えられ、身体的にも快適で健康的です。
そして、火災保険、地震保険料を安くすることは、家計への負担を軽くしてくれることはもちろん、自然災害から家族の命と生活を守ってくれます。
さらに外装メンテナンスも最小限にできるよう計画されたお家は、長期的に見れば大きな資産となります。
安く建てられる住まいから、安く住み続けられる住まいが、これからのお家づくりの常識なのです。
WRITER

清水 窓加
営業
入社5年目です! 小学校1年生から12年間サッカーを続けていました。 大学は愛知県の方に行っており、就職を機に富山に戻ってきました。 住宅のことに関して日々勉強中です!
カテゴリで絞り込む
ARCHIVE
過去の記事
閉じる